| 文の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 会話文 | 地の文 | 和歌 | |
| 源氏物語 | 35.1 | 61.8 | 3.1 |
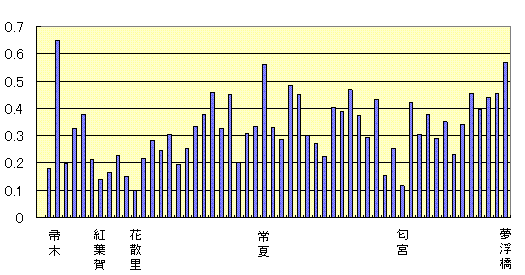
グラフ1 総語数に対する会話文の出現比率
源氏物語の会話文と地の文をめぐる数量分析
—助動詞を中心に—
2)結果と考察
2.1 主要品詞の出現比率
まず、「源氏物語」全体を概観するために会話文、地の文、和歌の語数の出現比率を求めると、表1の様になる。次に各巻の会話文の出現比率はグラフ1である。このグラフ1からも明らかなように、巻の50%以上が会話文で占められている巻は、多い順に「帚木」「夢浮橋」「常夏」で、逆に少ない順では、「花散里」「匂宮」「紅葉賀」の巻である。会話文の出現比率の多少は各巻の内容に因っている。
表1 会話文、地の文、和歌の出現比率(単位:%)
| 文の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 会話文 | 地の文 | 和歌 | |
| 源氏物語 | 35.1 | 61.8 | 3.1 |
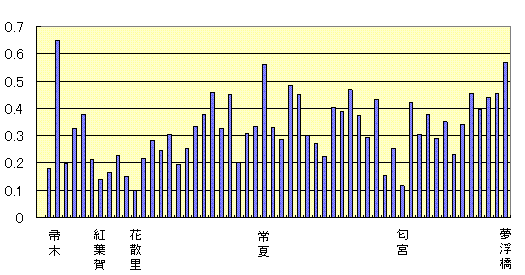
次に会話文、地の文、和歌の主要品詞の出現比率を求めると表2となる。主要品詞の出現比率からは、会話文、地の文に大きく差があるとはいえないが、和歌のように字数の制限の強いものでは、名詞の出現比率が高く、形容詞、形容動詞、副詞、のような修飾語の出現比率が低くなっている。樺島氏が、現代文で樺島の法則として述べていること4) が、「源氏物語」でも数量的に認められる。
| 名詞 | 代名詞 | 動詞 | 形容詞 | 形容動詞 | 副詞 | 助詞 | 助動詞 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会話 | 16.4 | 0.9 | 14.9 | 6 | 2.2 | 4.6 | 31.1 | 13.5 | 10.4 |
| 地の文 | 17.7 | 0.4 | 17.4 | 5.9 | 2.6 | 4.1 | 32.1 | 10.4 | 9.4 |
| 和歌 | 25.8 | 0.8 | 17.8 | 3.5 | 0.9 | 1.6 | 35.1 | 11 | 3.5 |
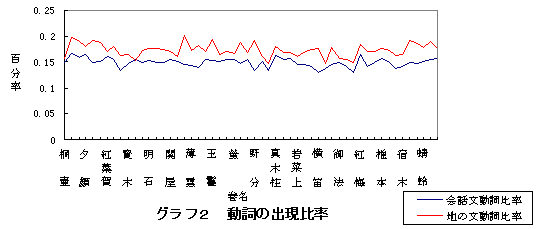
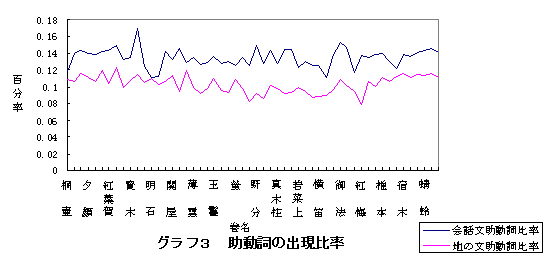
2.2助動詞全般と各巻での出現状況
助動詞は、すべての巻で会話文のほうに多く出現するので、助動詞全体と各巻の状況について調べた。各助動詞は『大成』の助詞助動詞の部の見出し語形のまま使用した。その理由は、助動詞を意味分類する前に、まず全体の正確な数量的状況を把握しておくことが必要と思われるからである。助動詞の意味分類については相互の配列順序に深く関わっており、細かな点で諸説異なり、5)6)7)8)慎重に行なわれなければならない。助動詞の活用形は無視し、助動詞の前に接続する自立語の品詞の種類は問わず、単純に出現率を求めた。その結果、「源氏物語」全体では、「ず」「む」「たり」「けり」「なり」「り」「ぬ」…の順に出現比率が高い。しかし、会話文と地の文では、この順位がかなり異なる(表3)。即ち会話文では、出現比率が高い順に「む」「ず」「き」「べし」……となるが、地の文では「ず」「たり」「り」「けり」……の順になる。会話文中での助動詞の「む」の出現比率は、16.0%と最も高く第一位である。
| ず | む | たり | けり | なり | り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 (順位) |
12.9 (1) | 11.0 (2) | 10.0 (3) | 8.4 (4) | 8.0 (5) | 7.8 (6) |
| 会話文 (順位) |
11.9 (2) | 16.0 (1) | 6.0 (7) | 5.9 (8) | 7.9 (5) | 3.2 (10) |
| 地の文 (順位) |
13.3 (1) | 7.3 (6) | 13.3 (2) | 10.2 (4) | 8.1 (5) | 11.4 (3) |
| ぬ | き | べし | つ | る | す | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 (順位) |
7.4 (7) | 6.9 (8) | 6.6 (9) | 3.4(10) | 3.4(11) | 2.9(12) |
| 会話文 (順位) |
7.9 (6) | 8.9 (3) | 8.5 (4) | 4.5(10) | 2.6(12) | 2.8(11) |
| 地の文 (順位) |
7.0 (7) | 5.0 (9) | 5.3 (8) | 2.7(12) | 4.0(10) | 3.2(11) |
このような会話文と地の文における各助動詞の出現比率の違いを度数分布としてグラフ化したものが図1から図12までである(上位12位まで)。縦軸は巻の数、横軸は出現比率を表し、助動詞の種類別に会話文の分布を上段に、地の文を下段に、0.2%間隔ごとに何巻分布するかを表わしている。この分布グラフをみると、会話文に多く出現しているのが「む」「き」「べし」などであり、地の文では「たり」「り」などである。「ず」「なり」「る」などはどちらの文にも同じ様な出現比率で使われている。
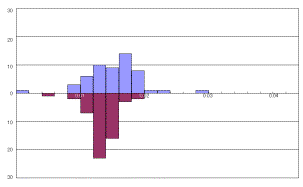 図1 「ず」 |
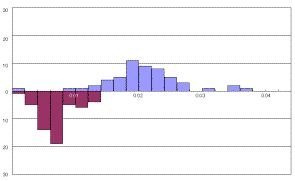 図2 「む」 |
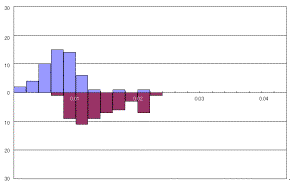 図3 「たり」 |
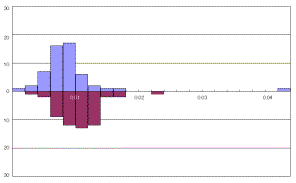 図4 「けり」 |
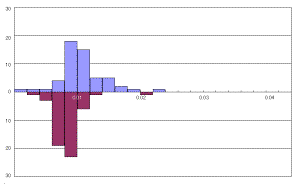 図5 「なり」 |
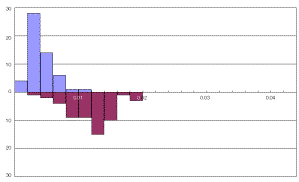 図6 「り」 |
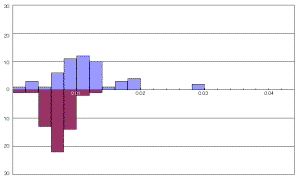 図7 「ぬ」 |
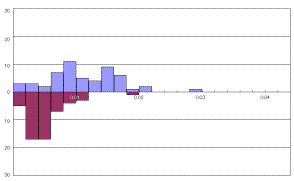 図8 「き」 |
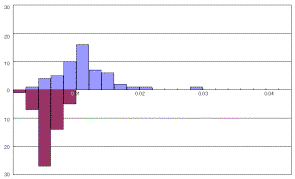 図9 「べし」 |
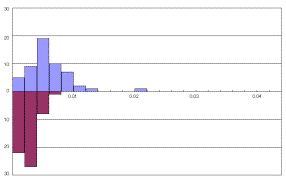 図10 「つ」 |
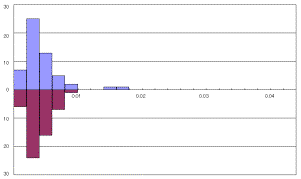 図11 「る」 |
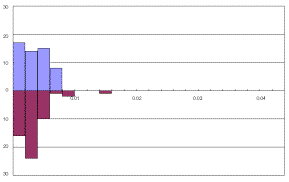 図12 「す」 |
「なり」については、前に接続する語が活用語の終止形である、伝聞・推定の意の「なり」と、それ以外の語に接続する、断定の意の「なり」が同一語であるか、別語であるかの論議がなされて来たが、9)10)11)12)13)14)現在では別語とするのが定説となっている。 前に接続する語が活用語の終止形のものは、見出し語形「なり」総数のうち4.1%で、全巻で143個と数は少ない(『大成』の認定基準によっている)が、語源も違い別語であるので、会話文と地の文での分布を調べた。会話文と地の文での各々の全助動詞中での出現比率はそれぞれ0.6%と0.2%で、会話文での出現比率がわずかに多い。 特定の相手を想定して話す会話文中のほうが地の文中より、伝聞・推定の「なり」が多くなっている。それらを除いた「なり」については、7.3%と 7.9%で前記の結果に、殆ど変わりがない。ただ、わずかの差でも、会話文のほうが話し手の主観度が強い伝聞・推定の「なり」が多く、断定の「なり」が地の文に多いことは納得できる結果である。
2.3助動詞の接続状況
次に、会話文と地の文で、自立語すべてに接続する助動詞の接続状況を調べた。助動詞の前接品詞の出現比率は表4の様であり、会話文、地の文ともに動詞に接続する助動詞が80%以上を占める。動詞に接続する助動詞の種類については次節で詳しく述べるとして、動詞以外に接続する助動詞の種類について調べた(表5)。
これを見ると、会話文地の文ともに「なり」が第一位となっている。これは名詞の後に来る助動詞に「なり」が多い故であり、第二位目からはここでも会話文地の文の特性を表しているといってよい。すなわち、会話文では「む」「ず」「べし」の順に多く接続し、地の文では「けり」「ず」「む」の順に多く接続している。
| 名詞 | 動詞 | 形容詞 | 形容動詞 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会話文 | 8.5 | 80.2 | 7.2 | 2.0 | 2.1 |
| 地の文 | 9.8 | 81.6 | 5.0 | 1.9 | 1.7 |
表5 動詞以外の品詞に後接する助動詞の種類別出現比率(単位:%)
| なり | む | ず | べし | き | けり | つ | まじ | たり | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会話文 (順位) |
36.3 (1) |
15.6 (2) |
14.2 (3) |
10.9 (4) |
8.3 (5) |
7.3 (6) |
1.5 (7) |
1.4 (8) |
0.7 (9) |
3.7 |
| 地の文 (順位) |
48.4 (1) |
7.5 (4) |
12.7 (2) |
6.4 (6) |
7.0 (5) |
10.1 (3) |
2.0 (7) |
0.6 (9) |
2.0 (8) |
3.3 |
| 動詞だけ | 動詞+助動1 | 動詞+助動2 | 動詞+助動3 | 動詞+助動4 | 動詞+助動5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会話文 | 23.1 | 60.0 | 15.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
| 地の文 | 30.3 | 59.0 | 9.9 | 0.7 | 0.0 |
| む | ず | たり | べし | き | す | けり | ぬ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会話文 (順位) |
17.5 (1) |
16.2 (2) |
9.0 (3) |
8.8 (4) |
6.7 (5) |
6.1 (6) |
3.7 (7) |
3.7 (8) |
28.5 |
| 地の文 (順位) |
7.8 (3) |
14.9 (2) |
23.7 (1) |
4.0 (9) |
3.8 (10) |
6.3 (6) |
7.7 (4) |
4.9 (8) |
25.2 |
| 会話文 | 地の文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヌ | 36.3 | 1 | ヌ | 33.6 |
| 2 | タリ | 14.3 | 2 | タリ | 18.5 |
| 3 | ズ | 11.5 | 3 | ル | 10.9 |
| 4 | ツ | 11.1 | 4 | ズ | 10.1 |
| 5 | ル | 8.5 | 5 | ツ | 8.3 |
表9連続用法二番目助動詞の比率(単位:%)
| 会話文 | 地の文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ム | 26.8 | 1 | ケリ | 29.3 |
| 2 | キ | 17.3 | 2 | ム | 16.7 |
| 3 | ベシ | 13.8 | 3 | ベシ | 13.7 |
| 4 | ケリ | 12.9 | 4 | キ | 12.1 |
| 5 | タリ | 5.4 | 5 | タリ | 8.3 |
2.5「む」と「たり」について
ここまで、会話文と地の文の助動詞について数量的に分析してきた結果、会話文では「む」が、地の文では「たり」の出現比率が他のものより高いことがわかったので、それぞれの文中での活用形ごとの出現比率を調べた (表10)。使われかたに差があるかどうかを調べるためである。「む」の場合、終止形と連体形は同形で、区別がしにくい場合がしばしばあり、各巻ごとでも少しずつ終止形と連体形の相互の出現比率が異なり、活用形の情報からだけでは会話文と地の文の大きな違いは見出せない。已然形については、会話文の217例中207例が、地の文の42例中42例全部が係助詞「こそ」の結びとなっているが、会話文のほうが係助詞「こそ」を多く使用し(表11)、強調表現が多いことから、会話文中での已然形の出現比率が地の文より若干高くなったといえる。「む」の場合、活用形の出現比率による地の文と会話文の差は殆どない。
「たり」については会話文と地の文では、活用形ごとの出現比率はかなり異なる。会話文の連用形の出現比率は、各巻によってそれぞれ少しずつ異なるが、終止形が5%前後で未然形が10%前後という点はかわらず、各巻でもおおかたこの傾向を示している 。この理由について「たり」の後接語のすべてについて調べた(表12)。
|
活用形 |
「む」 | 「たり」 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会話文 | 地の文 | 会話文 | 地の文 | |
| 未然形 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 4.5 |
| 連用形 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 6.4 |
| 終止形 | 30.2 | 22.9 | 4.8 | 21.5 |
| 連体形 | 62.2 | 74.7 | 65.9 | 58.6 |
| 已然形 | 7.7 | 2.4 | 4.0 | 9.0 |
| 命令形 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 「こそ」 | 「ば」 | 「ど」 | |
|---|---|---|---|
| 会話文 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |
| 地の文 | 0.5 | 5.3 | 2.3 |
| 後接 | 会話文 | 地の文 | 後接 | 会話文 | 地の文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 然 形 |
ム | 9.1 | 11.9 | 3.2 | 4.5 | 連 体 形 |
ナリ | 3.5 | 65.9 | 0.9 | 58.6 |
| ズ | 0.8 | 0.7 | メリ | 2.0 | 0.3 | ||||||
| バ | 1.3 | 0.3 | ヲ | 2.5 | 5.6 | ||||||
| その他 | 0.7 | 0.3 | ニ | 3.5 | 4.9 | ||||||
| 連 用 形 |
ケリ | 2.3 | 13.3 | 3.0 | 6.4 | ハ | 1.9 | 1.1 | |||
| キ | 8.5 | 2.4 | モ | 1.2 | 1.8 | ||||||
| ツ | 1.8 | 0.7 | その他 | 3.3 | 2.8 | ||||||
| その他 | 0.7 | 0.3 | 文末 | 44.5 | 40.4 | ||||||
| 終 止 形 |
ト | 2.0 | 4.8 | 0.8 | 21.5 | 已 然 形 |
バ | 2.1 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
| その他 | 1.1 | 0.1 | ド | 1.0 | 2.9 | ||||||
| 文末 | 1.7 | 20.6 | その他 | 0.3 | 0.0 | ||||||
| 文末 | 0.6 | 0.1 | |||||||||
「たり」でも終止形が多くなったといえる。地の文に已然形が多いのは、接続助詞「ば」と「ど」が、理由を述べたり逆接する助詞で地の文に多く(表11)、それに影響されて、地の文での出現比率が高くなっているためである。「こそ」の結びは会話文で5例、地の文で2例でともに0.6%以下であるので影響外であろう。各巻多少の違いはあるが、おおかたこの傾向を持っている。
会話文に「む」が多く、地の文に「たり」が多い理由について、助動詞の相互承接の語順という点から考えると、「む」は必ず「たり」より後に配列される語である。ということは、文中で果たす意味が「助動詞相互承接の語順は、上から辿れば感情的性格の濃くなってゆく順序であり、下から辿れば論理的性格の濃くなってゆく順序であると言えるであろう。」11) とも、また「段階的に、客観的な事態の記述から、話し手の主観性へと色濃く傾いてくることが認められる。」7) とも言える訳だから、会話文のほうが主観的意が強く、感情的性格が濃いといえるので「む」が多くなり、地の文のほうが、客観的に叙述する必要性が高く、論理的性格が濃いため「たり」が多くなった、といえる。
3)結論
以上結論として、
文献
1)藤井貞和 「草子地」論の諸問題 『国文学』 第22巻1号 昭和52年1月
2)伊藤 博 心内語 『国文学』28巻16号
3)阪倉篤義 『文章と表現』第二章 第五節 角川書店 昭和50年
4)樺島忠夫 『日本語はどう変わるか』岩波書店 昭和56年1月
5)橋本進吉 『助詞・助動詞の研究』岩波書店 昭和 44 年 11月
6)金田一春彦 不変化助動詞の本質 上・下 『国語国文』 昭和28 年 2,3
7)阪倉篤義 『語構成の研究』角川書店 昭和41年3月
8)北原保雄 助動詞の相互承接についての構文論的考察『国語学』 昭和45年 12月
9)春日和男 いはゆる伝聞推定の助動詞「なり」の原形について『国語学』 昭和30 年12月
10)竹岡正夫 助動詞ナリの表わすもの−助動詞の意味の検討-『国語学』 昭和31年7月
11)塚原鉄雄 活用語に接続する助動詞<なり>の生態的研究 『国語国文』 第28巻7号
12)北原保雄 <なり>と<見ゆ>−上代の用例に見えるいわゆる終止形承接の意味するもの 昭和40年 6月
13)北原保雄 <終止なり>と<連体なり>−その分布と構造的意味-『国語と国文学』 第43巻
14)北原保雄 「なり」の構造的意味 『国語学』 昭和42年3月
15)渡辺 実 叙述と陳述—述語文節の構造— 『国語学』 昭和28年10月
16) 大野 晋 助動詞の役割『解釈と鑑賞』 昭和43年 10月号
English Abstruct