
(駒場野公園で撮影)
ヤブカンゾウ またの名前を忘れ草。
毛詩に「能忘憂」とあるように、憂い
を忘れる花だったようです。平安時代
より、人や物事を忘れる場合にも用い
られました。
「須磨」 P25-10
ひたすら世になくなりなむは言はむ方なくて、やうやう忘れ草も生
ひやすらん、聞くほどは近けれど、いつまでと限りある御別れにもあらで、お
ぼすに尽きせずなむ。
「宿木」 P44−11
さて中中みな荒らしはて、忘れ草
生ふして後なん、この右のおとゞも渡り住み、宮たちなども方方ものし給へ
ば、むかしに返たるやうにはべめる。
「浮舟」 P248-15
親もし
ばしこそ嘆きまどひ給はめ、あまたの子どもあつかひて、おのづから忘れ草摘
みてん、ありながらもてそこなひ、人笑へなるさまにてさすらへむは、まさる
物思ひなるべし、など思ひなる。

(京王百草園で撮影)
当時は、現在のような大輪の栽培種ではなく、
このリュウノウギクのような小さく群生する
種を「きく」と呼んでいたようです。
「帚木」 P51-11
菊いとおもしろくうつろひわたりて、風に競へる紅葉の乱れなど、あはれとげに見えたり。
「帚木」 P52-02
菊をおりて、
「琴の音も月もえならぬ宿ながらつれなき人を引きやとめける
わろかめり」
「帚木」 P60-04
九日の宴に、まづかたき詩の心を思めぐらし暇なきおりに、菊の露を
かこち寄せなどやうの、つきなきいとなみにあはせ、さならでも、
「紅葉賀」 P243−03
かざしの紅葉いたう散りすぎて、顔のにほひにけおされたる心ちすれば、御前な
る菊を折て左大将さしかへ給。
「紅葉賀」 P243−04
さるいみじき姿に、菊の色色うつろひ、えな
らぬをかざして、けふはまたなき手を尽くしたる入り綾のほど、そぞろ寒く、
この世の事ともおぼえず。
「葵」 P315−07
深き秋のあはれまさり行風のをと、身にしみけるかなと、ならはぬ御ひとり
寝に、明かしかね給へる朝ぼらけの霧りわたれるに、菊のけしきばめる枝に、
濃き青鈍の紙なる文つけて、さしをきて往にけり。
「少女」 P324-06
冬のはじめの朝霜むすぶべき菊のまがき、我
は顔なる柞原、おさおさ名も知らぬ深山木どもの木深きなどを移し植へたり。
「藤裏葉」 P193-08
女君の大輔の乳母、「六位宿世」とつぶやきしよひのこと、物のをりをりに
おぼし出でければ、菊のいとおもしろくてうつろひたるを給はせて、
「あさみどりわか葉の菊を露にても濃きむらさきの色とかけきや
からかりし折の一言葉こそ忘られね」と、いとにほひやかにほゝ笑みて給へり。
はづかしういとをしき物から、うつくしう見たてまつる。
「ふた葉より名立たる園の菊なればあさき色わく露もなかりき
いかに心をかせ給へりけるにか」といと馴れて苦しがる。
「藤裏葉」 P197-07
あるじの院、菊をおらせ給て、青海波の折をおぼし出づ。
色まさるまがきの菊もをりをりに袖うちかけし秋を恋ふらし
「幻」 P203-01
九月になりて、九日、綿おほひたる菊を御覧じて、
もろともにおきゐし菊の白露もひとりたもとにかるる秋かな
「匂宮」 P219-13
老を忘るゝ菊に、おとろへ行藤袴、物げなきわれもかうなどは、
いとすさまじき霜枯れのころをひまでおぼし捨てず、
「宿木」 P030-06
御前の菊移ろひはてて盛りなるころ、空のけしきのあはれにうちしぐるるに
も、まづこの御方に渡らせ給て、むかしの事など聞えさせ給ふに、
「宿木」 P32-08
霜にあへず枯れにし園の菊なれど残りの色はあせずもある哉
「宿木」 P94-15
菊のまだよく移ろひはてで、わざとつくろひたてさせ給へるは、なかなかを
そきに、いかなる。一本にかあらむ、

(駒場野公園で撮影)
この花は名前から、若く美しい女性の象徴
とされていますが、枯れかかった時の匂いは
あまりよくありません。丈は2メートル近くまで
伸びます。
「野分」 P043-12
紫苑、撫子、濃き薄き衵どもに、女郎花の汗衫などやうの、時に会ひたるさまに
て、四五人連れて、こゝかしこの草むらに寄りて、色色の篭どもを持てさま
よひ、撫子などのいとあはれげなる枝ども取り持てまいる霧のまよひは、いと
艶にぞ見えける。
「野分」 P048-15
吹きみだる風のけしきにをみなへししほれしぬべき心ちこそすれ
「野分」 P049-04
下露になびかましかばをみなへしあらき風にはしほれざらまし
なよ竹を見給へかし
「夕霧」 P111-03
女郎花しほるゝ野辺をいづことて一夜ばかりの宿を借りけむ
「匂宮」 P219-10
秋は世の人のめづる女郎花、小牡鹿の妻にすめる萩の露にもをさをさ御
心移し給はず、老を忘るゝ菊に、おとろへ行藤袴、物げなきわれもかうなどは、
いとすさまじき霜枯れのころをひまでおぼし捨てず、などわざとめきて香にめ
づる思をなん立てて好ましうおはしける。
「総角」 P410-08
をみなへし咲ける大野をふせぎつゝ心せばくやしめを結ふらむ
「総角」 P410-10
霧ふかきあしたの原のをみなへし心をよせて見る人ぞ見る
「宿木」 P055-01
をみなへししほれぞまさる朝露のいかにをきける名残なるらん
「宿木」 P041-06
女郎花をば見過ぎてぞ出で給ぬる。
「東屋」 P155-02
帷子一重をうちかけて、紫苑色の花やかなるに、女郎花のをり物と見
ゆる重なりて、袖口さし出でたり。
「蜻蛉」 P312-08
女郎花みだるる野辺にまじるとも露のあだ名をわれにかけめや
「蜻蛉」 P312-12
花といへば名こそあだなれをみなへしなべての露にみだれやはする
「蜻蛉」 P313-01
旅寝して猶心みよをみなへしさかりの色にうつりうつらず
「手習」 P342-08
これもいと心ぼそき住まゐの
つれづれなれど、住みつきたる人々は、物きよげにおかしうしなして、垣ほに
植へたる撫子もおもしろく、女郎花、き経など咲きはじめたるに、色々の狩
衣姿の男どもの若きあまたして、君もおなじ装束にて、南をもてに呼び据へた
れば、うちながめてゐたり。
「手習」 P345-12
前近き女郎花をおりて、「何にほふらん」と口ずさびて、ひとりごち立てり。
「手習」 P348-07
あだし野の風になびくな女郎花われしめ結はん道遠くとも
「手習」 P348-13
うつしうへて思ひみだれぬ女郎花うき世をそむく草の庵に

(駒場野公園ケルネル水田)
この水田では、皇居の水田に植えられている
のと同じ品種の満月餅というモチ米が栽培
されています
「須磨」 P042-10
御馬ども近う立てて、見やりなる倉か何ぞなる稲取り出でて飼ふなど、
めづらしう見給ふ。
「明石」 P60-06
入道の領じめたる所所、海のつらにも山隠れにも、時時につけてけ
ふをさかすべき渚の苫屋、行ひをして後世のことを思ひすましつべき山水の
つらに、いかめしき堂を建てて三昧を行ひ、此世のまうけに秋の田の実を刈り
をさめ、残りの齢積むべき稲の倉町どもなど、おりおり所につけたる、見所
ありてし集めたり。
「夕霧」 P126-12
山風にたへぬ木ゝの梢も峰の葛葉も、心あはたゝしうあらそひ散るまぎれに、
たうとき読経の声かすかに、念仏などの声ばかりして、人のけはひいと少なう
木枯らしの吹き払ひたるに、鹿はたゞまがきのもとにたゝずみつゝ、山田の引
板にもおどろかず、色濃き稲どもの中にまじりてうち鳴くも、愁へ顔なり。
「手習」 P339-15
門田の稲刈るとて、所につけたる物まねびしつゝ、若き女ども
は歌うたひけうじあへり。
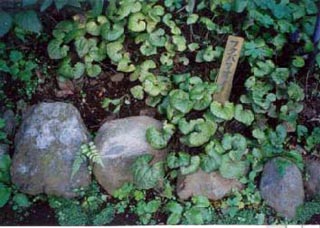
(駒場野公園野草園で撮影)
使われました
「葵」 P299-01
扇のつまをおりて、
はかなしや人のかざせるあふひゆへ神のゆるしのけふを待ちける
しめのうちには。
とある手をおぼし出づれば、かの内侍のすけなりけり。あさましう古りがたく
もいまめくかな、とにくさに、はしたなう、
かざしける心ぞあだに思ほゆる八十氏人になべてあふひを
女はつらしと思きこえけり。
「須磨」 P18-08
賀茂の下の御社をかれ
と見はたすほど、ふと思ひ出でられて、下りて御馬の口を取る。
ひき連れて葵かざししそのかみを思へばつらし賀茂の瑞垣
と言ふを、げにいかに思ふらむ、人よりけにはなやかなりしものを、とおぼす
も心ぐるし。
「藤袴」 P105-15
宮の御返りをぞ、いかゞおぼすらむ、たゞいさゝかにて、
心もて光にむかふあふひだに朝をく霜をおのれやは消つ
「若菜下」 P369-15
童べの
持たる葵を見たまひて、
くやしくぞつみをかしけるあふひ草神のゆるせるかざしならぬに
「幻」 P198-15
、裳、唐衣も脱ぎすべしたりけるを、
とかく引きかけなどするに、葵をかたはらにをきたりけるを、よりて取り給て、
「いかにとかや、この名こそ忘れにけれ」との給へば、
さもこそはよるべの水に水草ゐめけふのかざしよ名さへ忘るる
とはぢらひて聞こゆ。げに、といとおしくて、
大方は思ひすててし世なれどもあふひは猶やつみおかすべき