
写真は、栽培品種として改良され、
花がたくさん咲くようになっていま
すが、当時の「りんだう」は山野に
自生する原種だったと思われます。
「葵」 p319-09
枯れたる下草の中に、竜胆、撫子などの咲き出でたるをおらせ給て、中将の立ち給ぬる後に、若君の御乳母の宰相の君して、「草枯れのまがきに残るなでしこを別れし秋のかたみとぞ見る。匂ひ劣りてや御覧ぜらるらむ」と聞こえ給へり。
「野分」 p046-04
はらはべなど、おかしき衵姿うちとけて、心とゞめとりわき植へ給ふ竜胆、朝顔のはいまじれる籬も、みな散り乱れたるを、とかく引き出で尋めるなるべし。
「夕霧」 p127-02
草むらの虫のみぞより所なげに鳴きよはりて、枯れたる草の下より竜胆のわれひとりのみ心ながう這ひ出でて露けく見ゆるなど、みな例のころのことなれど、おりから所からにや、いとたへがたきほどのものがなしさなり。

現在も土手や田んぼの畦、
道路際など、どこにでも見
かけます。東京でもその気
になれば、線路際などで、
丈高く成長しているのを見
かけます。
「蓬生」 p135-02
ただ御せうとの禅師の君ばかりぞ、まれにも京に出でたまふ時はさしのぞき給へど、それも世になき古めき人にて、おなじきほうしといふなかにも、たづきなくこの世を離れたる聖にものし給て、しげき草蓬をだに掻き払はむものとも思ひより給はず。
「蓬生」 p145-06
霜月ばかりなれば、雪霰がちにて、ほかには消ゆる間もあるを、朝日夕日をふせぐ蓬葎の陰に深う積もりて、越の白山思ひやらるる雪のうちに、出で入る下人だになくて、つれづれとながめ給ふ。
「蓬生」 p148-08
むかしのあとも見えぬ蓬のしげさかな」との給へば、「しかしかなむたどり寄りてはべりつる。侍従がをばの少将とゐひはべりし老い人なん、変はらぬ声にてはべりつる」とありさま聞こゆ。
「蓬生」 p149-02
さらにえ分けさせ給ふまじき蓬の露けさになむはべる。
「蓬生」 p149-05
たづねともわれこそとはめ道もなく深き蓬のもとの心を
「蓬生」 p152-09
中にも、この宮にはこまやかにおぼしよりて、むつましき人々に仰せ事給ひ、下部どもなど遣はして、蓬払はせ、めぐりの見ぐるしきに板垣といふものいち堅めつくろはせ給ふ。
「蓬生」 p152-14
人々の上までおぼしやりつつ、とぶらひきこえ給へば、かくあやしき蓬のもとにはをきどころなきまで、女ばらも空を仰ぎてなむ、そなたに向きてよろこびきこえける。
「松風」 p195-15
............さらにみやこに帰りて、古受領の沈めるたぐひにて、貧しき家の蓬葎、もとのありさまあらたむることもなきものから、............
「朝顔」 p262-02
いつのまによもぎがもととむすぼほれ雪ふる里と荒れし垣根ぞ
「柏木」 p039-09
庭もやうやう青み出づる若草見えわたり、ここかしこの砂子薄きものの隠れの方に蓬も所ゑ顔なり。前栽に心入れてつくろひ給しも、心にまかせて茂りあひ、一むら薄も頼もしげに広ごりて、虫の音添はん秋思ひやらるるより、いとものあはれに露けくて分け入り給。
「東屋」 p178-04
かやうの朝ぼらけに見れば、物いただきたる者の鬼のやうなるぞかしと聞き給ふも、かかる蓬のまろ寝にならひ給はぬ心ちもおかしくもありけり。宿直人も門あけて出るをとする、をのをの入りて臥しなどするを聞給て、人召して、車、妻戸に寄せさせ給ふ。

尾花ともいいます。都会のまん中、
東京渋谷の宮益坂公園に群生して
いるので驚きました。今年の仲秋の
名月の日には3本350円くらいで花
屋さんに売っていました。
「藤裏葉」 p194-03
前栽どもなど、ちいさき木どもなりしもいとしげき陰となり、一村薄も、心にまかせて乱れたりける、つくろはせ給。
「柏木」 p039-10
前栽に心入れてつくろひ給しも、心にまかせて茂りあひ、一むら薄も頼もしげに広ごりて、虫の音添はん秋思ひやらるるより、いとものあはれに露けくて分け入り給。
「宿木」 p094-06
穂に出でぬもの思ふらししのすゝき招くたもとの露しげくして
「宿木」 p094-11
秋はつる野辺のけしきもしのすゝきほのめく風につけてこそ知れわが身ひとつの前栽どもなど、ちいさき木どもなりしもいとしげき陰となり、一村薄も、心にまかせて乱れたりける、つくろはせ給。
< おばな >
「宿木」 P94-03
枯れ枯れなる前栽の中に、おばなの、物よりことにて手をさし出で招くがおかしく見ゆるに、まだ穂に出でさしたるも、露をつらむきとむる玉の緒、はかなげにうちなびきたるなど、.....
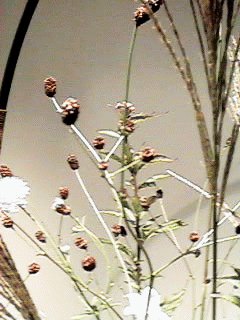
昔、ススキの草原の間によ
く見られる野草でした。
「匂宮」 p219-14
.........御前の前栽にも、春は梅花園をながめ給、秋は世の人のめづる女郎花、小牡鹿の妻にすめる萩の露にもをさをさ御心移し給はず、老を忘るゝ菊に、おとろへ行藤袴、物げなきわれもかうなどは、いとすさまじき霜枯れのころをひまでおぼし捨てず、などわざとめきて香にめづる思をなん立てて好ましうおはしける。

この花を一束花びんに生けておくと、
部屋中に、ちょっとお線香のような
ほんのりとした甘い香りが立ちこめ、
気分をリラックスさせてくれました。
「藤袴」 p94-2
おなじ野の露にやつるる藤袴あはれはかけよかことばかりも
「匂宮」 p219-8
秋の野に主なき藤袴も、もとのかほりは隠れて、なつかしきをひ風ことに、おりなしからなむまさりける。
「匂宮」 p219-14
......御前の前栽にも、春は梅花園をながめ給、秋は世の人のめづる女郎花、小牡鹿の妻にすめる萩の露にもをさをさ御心移し給はず、老を忘るゝ菊に、おとろへ行藤袴、物げなきわれもかうなどは、いとすさまじき霜枯れのころをひまでおぼし捨てず、などわざとめきて香にめづる思をなん立てて好ましうおはしける。